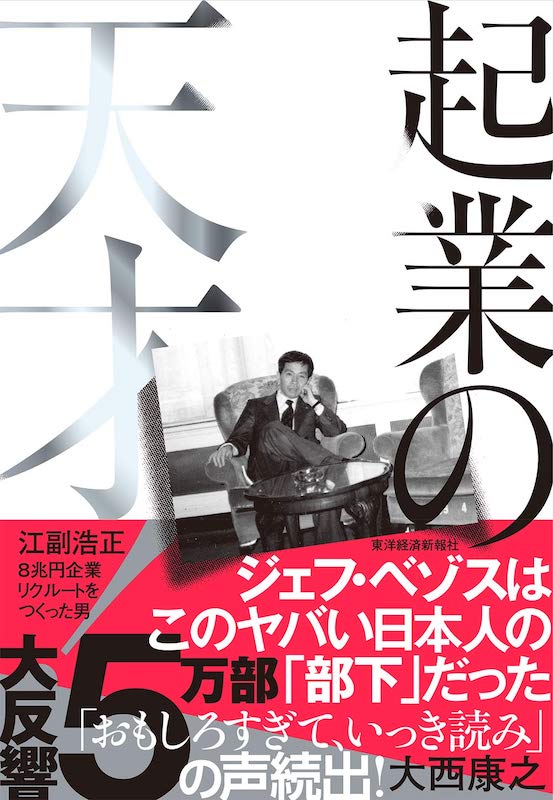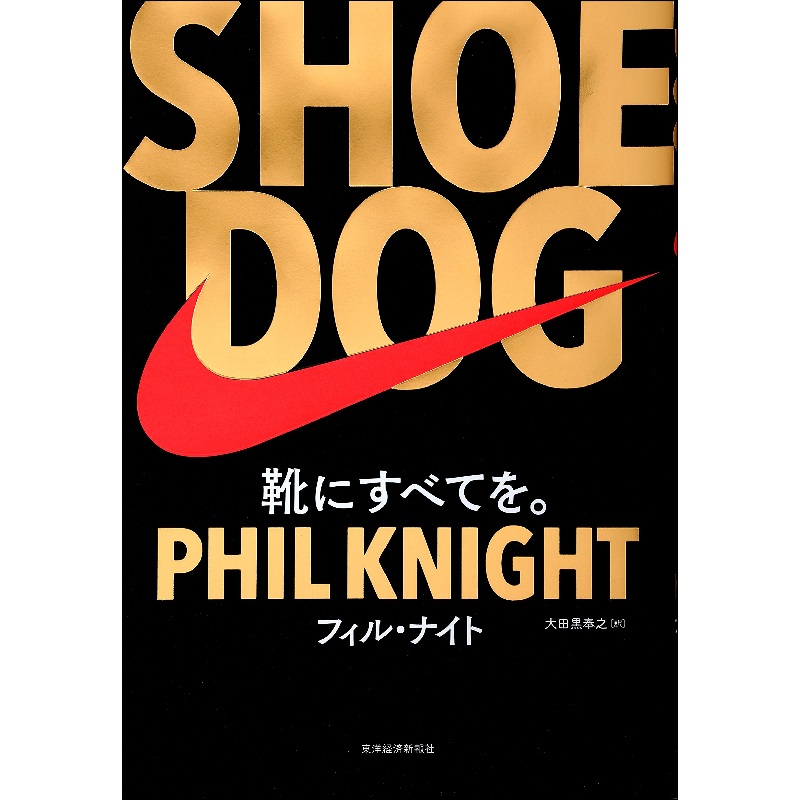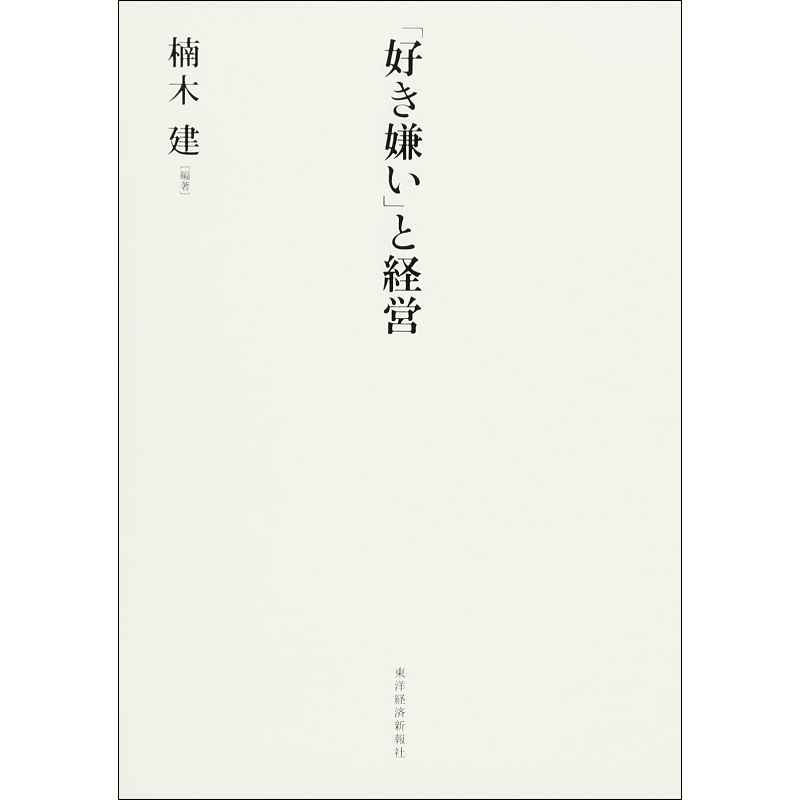GAFAも学ぶ!最先端のテック企業はいま何をしているのか―世界を変える「とがった会社」の常識外れな成長戦略
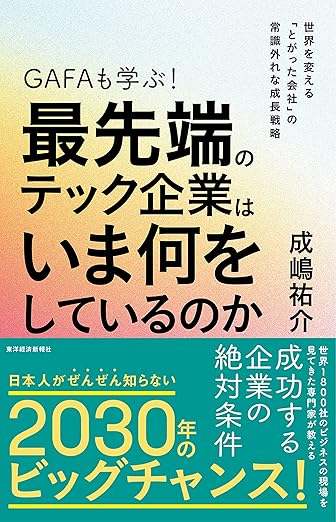
成嶋祐介氏の『GAFAも学ぶ!最先端のテック企業はいま何をしているのか』は、著者が中国を中心に1800社を超える最先端テック企業の実地観察をもとにまとめた現場密着型の一冊です。
成嶋氏は越境ECの実務を通して中国の最先端サービスに直接触れており、本書は「世界のテック潮流はシリコンバレー一辺倒ではない」という問題提起から入り、現場で起きている“常識外れの成長戦略”を具体例とともに解説します。
書誌情報や出版情報は東洋経済新報社ほかで確認できます。
本書が伝える「最先端テック企業の共通点」と全体像
本書の中心的な主張は、最先端のテック企業には共通する「決定的変革」があり、それを読み解けば日本のビジネスにも応用できる、という点です。
成嶋氏は10以上のキーワード(例:「便利」から「楽しい」への価値シフト、ユーザーとの“共犯関係”づくり、五感を刺激する購買体験、24時間365日の需給マッチング、信用の可視化、オンライン/オフラインの融合、動的な値付け=ダイナミックプライシング、PCレス戦略など)を提示し、章ごとに実例を交えて整理しています。
世界最先端で何が起きているかを俯瞰したい読者に最適な構成です。
事例で見る「常識外れ」の中身(ライブコマース、信用可視化、PCレス……)
本書の読みどころは「現場の“具体例”」にあります。いくつか代表的なトピックを抜粋してご紹介します。
● ライブ配信(ライブコマース)の破壊力
成嶋氏はライブ配信とECの融合が生む即時的な購買体験を繰り返し取り上げています。
中国のタオバオライブなどでは、高額商材(不動産など)までライブで短時間に売れてしまう実例があり、配信者・視聴者・専門家がリアルタイムにやり取りすることで「購入の瞬間」に至らせる仕掛けが常態化しています。
こうしたライブ×ECは「楽しい」を価値軸に据える最新の販売モデルを象徴します。
● 「信用の見える化」と評価の経済
ユーザー・サプライヤー・レビューのデータを組み合わせて信用を可視化し、共通の評価軸を作ることで新しいマーケットが形成されます。
WeChatのようにプラットフォーム上で法人向けサービスまで包含する事例や、信用データを事業設計に組み込む方法論が本書の重要な観点です。
プラットフォーム上での「信用」が流通の潤滑油となり、新規参入や高付加価値提供を後押しします。
● ダイナミック・プライシング(動的な値付け)と需給の即時マッチ
ライドシェアの例(中国の滴滴=DiDi)などを取り上げ、需要に応じて価格を変動させることで供給を柔軟に誘導し、24時間稼働のマーケットをつくる戦略が解説されています。
需要の“瞬間最適化”によって、従来の在庫や価格戦略では得られない収益機会が生まれる点を著者は強調しています。
● PCレス戦略・スマホファースト、ARなどのUX進化
若年層のスマホ依存が進む中、PCを介さない「スマホネイティブ」向けUX設計(ショート動画×EC、アプリ内完結購買、ARグラス等の次世代インターフェース)が「専門性の民主化」を推し進めています。
著者はARやコンセプトムービーの事例などを通じて、テクノロジーが「おもてなし」を自動化する未来像も提示しています。
示唆と実務への落とし込み──日本企業は何を学べるか
成嶋氏は「真似」ではなく「原理を掴んで自社に翻訳する」ことを薦めます。主な示唆は次のとおりです。
- 価値軸を『便利』から『楽しい/感情』へ広げる──商品の機能価値だけでなく、体験価値を設計すること。
- 信用や評価を事業資産に変える設計──プラットフォームでの信用データをサービス設計や価格戦略に組み込むこと。
- 需給のリアルタイム最適化を可能にする組織とデータパイプ──ダイナミックプライシングやライブ販促を支えるオペレーション能力が鍵。
- スマホ/ARなどネイティブUXの前提で事業設計する──デバイス前提を見直し、PC時代のプロセスを捨てる勇気。
これらは単なるIT導入ではなく、組織・人材・KPI設計を含む事業再設計の課題であり、成嶋氏は実務に踏み込んだ改善提案を行っています。
現場での実例と緻密な観察に基づくため、経営層から事業開発担当者まで広く示唆が得られる内容です。
まとめ
『GAFAも学ぶ!最先端のテック企業はいま何をしているのか』は、現場の観察に基づく実務寄りのリサーチ本です。
中国やその他地域の最先端プレイヤーの「やっていること」を具体的に学び、自社にどう応用するか考えたい方に特に向いています。
テックトレンドを“ショートカット”で把握したいマーケター、新規事業担当者、越境EC/プラットフォーム事業の実務家におすすめします。